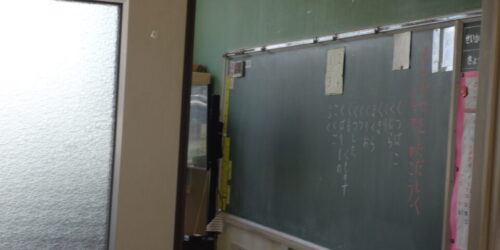6年生七夕集会に向けて
6年生が七夕集会に向けて、地域の七夕伝説のこと、鵲の地名について
お二人のゲストティーチャーを迎えて学習を深めました。
13日(金)には、はて神社の宮司さんでもある萩原さん
18日(水)には、鵲小学校で教員も務められ、元花岡小学校の西村篤史先生に
お話をしていただきました。
萩原さんからは、「古い文献から読み解く鵲の七夕伝説」という演題でお話していただきました。



宮司としてこの星合はて神社のことを詳しく知っておきたいという思いから、神社記を調べられたそうです。
そこには、「かつて伊勢の国星合の浜には、松の林があり常に特別な気を放っていた。毎年7月7日夜に織姫、彦星が
降りてきた。黒い雲がこの林に降りてきてこの雲をよく見ると、鵲鳥が羽を広げ階段を作っている。織姫は身の丈
7尺から8尺(約212㎝~242cm)彦星は(272cm)ぐらいに見えた(中略)ふたりを祀る星合神社が建立され
いのれば願いが叶い参拝者が後を絶たない星合の郷だった。


西村先生は、「鵲」という地名について
星合、笠松、小舟江、五主と町名があるなか、どうして鵲という名があるのだろうと疑問を持たれ、文献を読み調べられたそうです。
七夕伝説は、いったいだれがいつ頃日本に伝えたのか。今から1550年前、呉の国から機を織る人々が、衣服を作る人々がやってきて、機織りや衣服を作る技術を伝えた。それらの人々は伊勢の地に住んで機を織り、服を作る祖先になったとか。呉は当時中国にあった国の名前です。この国が伝えた名残が今の日本に残っています。それが「呉服」だそうです。
等など、鵲についてたくさんお話しいただきました。
大変勉強になりました。ありがとうございました。